住宅ローンの滞納が始まった場合、多くの人は無気力になり、滞納を放置してしまいがちです。
その点、こうして任意売却について調べているあなたは、最悪の事態を避けて生活を再建する第一歩を踏み出しています。
今が踏ん張りどころですから、ぜひ前向きに取り組みましょう。
筆者は、不幸にも病気になったり、事業に行き詰まった方の任意売却サポートを行った経験がありますが、どなたも最後には「家を売ったが、借金がなくなってすっきりした」と笑顔になりました。
この記事では、競売までの限られた時間の中で、どのように家計を立て直し、どのように生活を再建するかを6ステップで解説します。
今「大変だ」と感じてしまうのは、何をすればいいかわからないから。「これをやれば大丈夫」とわかれば、スムーズに対策できるはずです。
この記事は、宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石秀彦が制作しました。
いますぐ対策できる6つのステップ

競売になると、最低落札価格は市場価格の7割程度と激安になってしまいます。売却基準額が市場価格の70%程度であり、最低落札価格がその80%程度に設定されているためです。
それに対して任意売却であれば、市場価格と近い水準での売却を目指します。一般に任意売却のほうが有利と考えて間違いないですし、その分すばやく家計を立て直し、新たな生活に踏み出すことができます。
また、任意売却を行う場合、タイミングは早ければ早いほど有利です。次の6つのステップのうち、最速のタイミングで売却を決断しましょう。
競売では、裁判所が決定する『売却基準価額』と、その80%に相当する『買受可能価額』(最低入札可能額)が用いられます(民事執行法60条、裁判所BITの用語解説)。売却基準価額は評価に基づき裁判所が定める“基準額”で、市場価格に機械的な固定比率で連動する制度ではありません(年次・根拠:民事執行法/裁判所サイト)。
STEP1|督促状が届いたらまず確認すること
督促状や催告書は銀行による「債権回収プロセス」のスタートラインです。
けっこう封筒を開けずに放置する方も多いのですが、なにも対応しない場合は最短 6 か月前後で競売手続きが始まります(ただし、具体的期間は金融機関・保証会社の運用や滞納状況により大きく異なります)。
まずは「延滞解消期限」を確認し、銀行の『回収管理部門』へ電話 を1 本入れましょう。誠実なリアクションで「回収担当の心証を良くする」だけでも交渉余地が生まれます。
この「延滞解消期限」は、金融機関により名前が異なるものの、意味は「この日までに延滞分を支払わないと、期限の利益を喪失しますよ」というデッドライン。期限の利益を喪失すると後戻りできず、競売に向けたプロセスが進行し始めます。
任意売却をサポートする不動産会社の立場でいうと、この時点までに、すばやく対策を取れればかなり対策しやすくなります。
期限の利益とは、住宅ローンなどでお金を借りた人が、契約した返済日まで元金を一括で返済しなくてもよいという権利(利益)のこと。返済を滞納するとこの利益を失い、金融機関から残額の一括返済を求められます。なお、「期限の利益」は民法136条の趣旨(“期限は債務者の利益のために定める”)に基づく概念で、一定の喪失事由は民法137条に規定されています(年次・根拠:民法136条・137条)。
STEP2|任意売却に強い不動産会社へ相談
任意売却は通常の仲介と違い、債権者との交渉や配分案作成が必要になるケースがあります。そこまで必要ない場合でも、銀行(または銀行の保証会社)との折衝は必ず必要になります。
かなり特殊な知識も必要になるため、実績がない不動産会社に依頼すると、まとまるはずの交渉がまとまらずに競売に移行してしまうリスクもあります。
必ず依頼する不動産会社の実績(どれくらいの任意売却を成約させてきたか)や、司法書士や弁護士とどのような連携が取れるかを確認してください。
また、どの銀行の任意売却を取り扱ったかも確認した方がいいでしょう。銀行(保証会社)によってクセも違いますので、その点も経験がある方が確実です。
STEP3|住宅ローン残高と滞納額を整理
金融機関から『残高証明書』を取り寄せ、遅延損害金を加えた「本当の債務額」を算出します。延滞が 3 か月を超えると、遅延損害金だけで月数万円単位の負担が発生することもあります。
この点、慣れている不動産会社なら委任状を作成して、銀行と直接やりとりしてくれるケースもあります。書類のやりとりを含め、交渉全般を引き受けてくれる不動産会社なら、手間が省けて心理的にもラクになります。
STEP4|債権者(銀行・保証会社)と交渉
銀行との交渉は、ほぼ不動産会社が一手に引き受けます(弁護士等に依頼した場合は、その弁護士などが交渉しますが、費用が高いので一般的ではありません)。
問題は、消費者金融などの後順位抵当権が付着している場合。
たいてい銀行が順位1番の抵当権者ですから、銀行に売却代金を総取りする権利があるのですが、後順位の抵当権も抹消しないと任意売却ができません。
そこで銀行にすこしだけ譲歩してもらい、後順位抵当権者に多少のお金を分配してもらう交渉を行います。その分配額は50万円などのごく小額で、業界では「ハンコ代」と呼ばれています。
ハンコ代とは「抵当権抹消書類にハンコを押してもらう代金」という意味です。
こういった面倒なやりとりを含めて、交渉期間はおおむね 2〜4 週間、交渉がまとまれば競売手続きは一時停止されます。
STEP5|売却活動と価格決定
筆者は、任意売却では、市場価格の80〜100%を目指していました。しかしそのためには、室内の整理と写真撮影への協力が不可欠です。
高く買ってもらうためには、やはり「素敵だな」「この家に住みたいな」と思ってもらう必要があるからです。
滞納中であり、病気など不測の事態に見舞われているかもしれませんが、ここはがんばりどころです。できる限り室内を片付け、購入希望者の内覧には積極的に対応してあげてください。
内見時に「滞納中」であることを知られたくない場合、仲介会社に話しておけば、とりあえず伏せておいてくれます。ただし、成約時にはどうしても伝える必要があります。
また、一戸建住宅を相場の価格で売り出した場合、成約までの期間は11か月程度が目安です。その点も加味して、より早く売却できるために相場の価格より若干安めに売出価格を設定することもあります。
STEP6|決済・残債の返済計画を立てる
無事に家を買いたい人が現れて、売買契約を締結したら、不動産会社は債権者(銀行など)と最後の詰めに入ります。
「本当に抵当権抹消書類を出してくれるのか」など、重要な項目を確認しながら手続きを進めていき、確実に新しい持ち主に所有権移転登記ができるように準備します。
買主もたいていは住宅ローンを組みますから、そちら側の銀行とも打ち合わせをしておき、残金決済と所有権移転登記が確実に行える準備をしておきます。
住宅を売っても返せなかった残額(残ったローン)は、月々5000円~数万円という無理のない範囲で返済するよう計画するのが一般的です。ここまでいくと、家計を再建しつつ新しいスタートラインを切ることができます。
沖縄県内ならトーマ不動産にご相談ください
沖縄県内の任意売却なら、トーマ不動産がサポート可能です。税制を含めて、さまざまな観点からアドバイスを行いつつ、任意売却プロセスを進めていきます。
お問い合わせ|トーマ不動産
沖縄県以外なら任意売却.comがサポート
沖縄県外であれば、専門会社の「任意売却.com」を利用してみてください。「まだ任意売却に進むべきか決断できない」という場合は、LINE相談が利用できます。公式LINE登録はニックネームでもOK。「まずは相談だけ」というスタンスでも受け付けてくれます。
任意売却.com|公式サイト
任意売却・競売・リースバックを比較してみると?

任意売却を考え始めると、ほぼ必ず浮かぶのが「競売と比べてどうだろうか?」「売却後にリースバックで住み続けるのはどうだろうか?」という選択肢。
ただし、これほど重大な問題で選択を誤ると致命的です。「損失額」や「その後の生活」から見た、それぞれの制度のメリット・デメリットを比較しましょう。
価格・時間・プライバシー・住み続け可否・信用情報 の 5 つの軸で特徴を整理し、それぞれ向いている人と向かない人を具体的に示します。
任意売却|価格とプライバシーを両立できる現実解
| 価格 | 市場相場の 80〜100% が狙える。債権者の合意が得られれば、競売より 1〜3 割高い手取りになることが多い。 |
| 時間 | 交渉〜売却まで 3〜6 か月が目安。競売までのタイムリミット管理が必須。 |
| プライバシー | 広告に "任意売却物件" と表示されないため、近所に知られにくい。 |
| 向いている人 | できるだけ高く売り、家計を立て直したい/家族や近所に事情を知られたくない。 |
一般的に、住宅ローンの滞納が始まった時点で最も有利なのは任意売却でしょう。「市場価格での売却も期待できる」という点で、その他の方法よりも金銭的なメリットが大きく、その分新生活も楽にスタートを切れます。
競売|手間はかからないが損失が最大化しやすい
| 価格 | 市場相場の 50〜70% 程度で落札される例が多く、残債が大きく残りやすい。 |
| 時間 | 手続きを債権者と裁判所が進めるため、債務者の手間はほぼゼロ。ただし開札日まで3~9か月かかることも。 |
| プライバシー | 裁判所サイトや入札公告で住所・物件写真が公開される。 |
| 向いている人 | 交渉や売却活動に一切関わりたくない/既に開札間近で時間がない。 |
どちらかというと「何もしないでいると競売になってしまう」というイメージ。時間的にも精神的にも余裕がなく、放置した結果「競売になってしまった」という事例は多く、結果的に大きな損失を出しているのが現状です。
ぜひ、競売になる前に手を打ちましょう。
リースバック|"住み続けたい" を叶える代わりに家賃負担が重い
| 価格 | 投資家が購入→賃貸するため、買取価格は相場の 60〜80% が多い。 |
| 住み続け可否 | 賃貸契約を結ぶことでそのまま居住可。ただし家賃が相場より割高になる傾向。 |
| 再購入オプション | 数年後に買い戻し可能な契約もあるが、買戻価格は割増設定が一般的。 |
| 向いている人 | 学区や介護の都合から転居したくない/まとまった現金が今すぐ必要。 |
最後に「家を売っても住み続けられますよ」といううたい文句をよく見かける「リースバック」ですが、競売よりはちょっと有利かもしれません。しかし、積極的におすすめできるものでもありません。
- 投資家が購入して運用するため買取額は市場価格の6割~7割
- 賃貸契約を結んで住み続けられるが、家賃は割高な場合が多い
安く買われて高い家賃で住むということになり、あまりお得感はありません。それでも、競売よりマシといえばマシですから、どうしても住み続けたいという理由があれば、検討してみてもいいでしょう。
5 つの軸で早見表
| 項目 | 任意売却 | 競売 | リースバック |
| 売却価格の目安 | 市場の 8〜10 割 | 市場の 5〜7 割 | 市場の 6〜8 割 |
| 手続き時間 | 3〜6 か月 | 6〜9 か月 | 1〜2 か月 |
| プライバシー | 公になりにくい | 公告で公開 | 公になりにくい |
| 住み続け可否 | × | × | ○(賃貸) |
| 信用情報への影響 | 約 5 年 | 約 7 年 | 賃貸契約次第 |
| 主導権 | 債務者+専門家 | 債権者+裁判所 | 投資家 |
任意売却にかかる費用は?
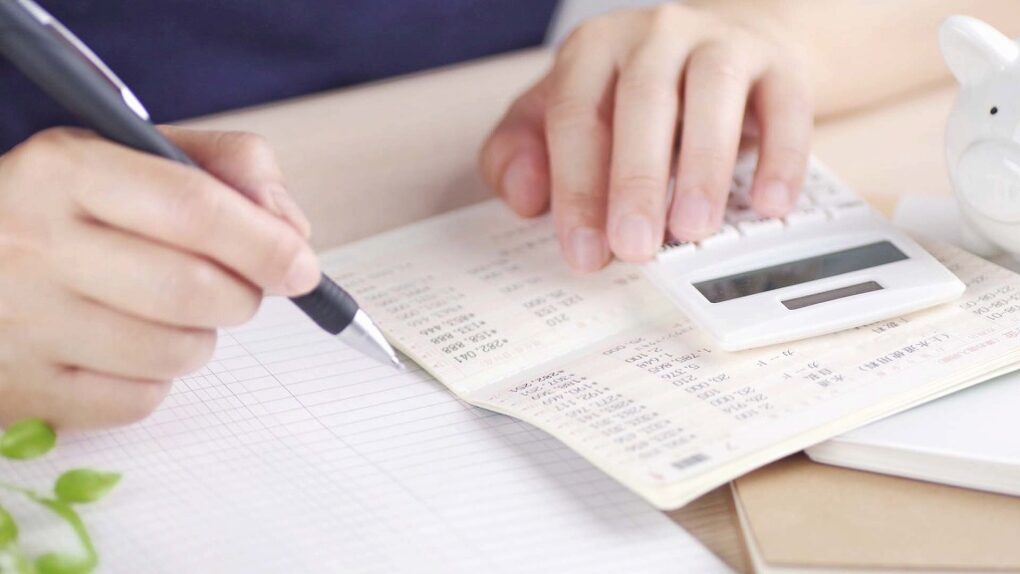
任意売却では「売却代金 = 債権者への配分原資」です。下記 3 つの費用は原則すべて売主負担ですが、実務上は売却代金から差し引かれるため「持ち出しゼロ」になるのが一般的です。
仲介手数料の考え方
仲介手数料は、売主・買主それぞれが、自分が依頼した仲介業者に対して支払います。売主側の不動産会社としては、任意売却の場合は「かなり大変な作業を行うが、仲介手数料は通常通り」という状況です。
任意売却の場合も「成功報酬」が前提ですから、もし成約しなかった場合は、特にお金を払う必要はありません。
なお、仲介手数料上限額は「物件価格の3%+6万円(税別)」で計算します。仲介手数料について、詳しくは以下の記事で解説しています。
売買の媒介報酬上限は報酬告示(昭和45年建設省告示第1552号・最新改正:令和6年6月21日 国交省告示第949号)。400万円超は『価額×3%+6万円+消費税』、加えて令和6年改正で“800万円以下は上限30万円(税別)”の特例が拡充されました。
抵当権抹消・差押え解除にかかる費用
抵当権抹消登記は、司法書士報酬を含めて5~7万円くらい(司法書士の先生によってかなり違います)。差押登記が入っている場合は、その分の抹消登記申請費用も必要になります。
これらはいずれも「売主責任」が原則ですが、任意売却では分配案に計上してしまい、不動産の売却代金から支払うことが一般的です。
たいていは不動産会社のほうで計画を進めていき、「これでいきましょう」と売主さんに了承をもらいます。
引っ越し費用はどう捻出する?
引っ越し費用も売主負担が原則。自分の引っ越し費用ですから、自分で出すのが当然なのですが、そうはいってもローンを滞納している状況では難しいのが一般的。
近場での引っ越しでも、10~30万円程度はかかります。
そこで、不動産会社が債権者と交渉し、不動産の売却額から引っ越し代を現金で残しておくケースもあります。この点は任意売却を担当した不動産会社の腕次第といえるでしょう。
筆者のケースは?
筆者は50万円程度を目安として「引っ越し代」の交渉を行っていました。脳出血で倒れて仕事ができなくなったKさん(沖縄県島尻郡八重瀬町)の事例では、保証会社と交渉のすえ、50万円の引っ越し代を確保。さらに買主側の不動産会社と交渉し、残置物(粗大ゴミ)等の撤去費用を、買主負担としてもらいました。それによりKさんも何とか引っ越しを完了し、新生活に移行することができました。
このように、債権者が「合理的」と判断すれば、一部費用を差し引いた残額を返済に充当することで合意が得られます。この点、交渉を任せる不動産会社の経験値が結果を左右します。
お問い合わせ|トーマ不動産
トーマ不動産では残債交渉も無料サポート。ファイナンシャルプランナーがその後の生活再建をお手伝いします。
任意売却についてのよくある質問10選

実際に相談窓口へ寄せられる質問トップ10を、Q&A形式でまとめました。このQ&Aで疑問を解消し、次の一歩を踏み出してください。
任意売却と通常売却とでは何が違う?
最大の違いは「抵当権者(銀行・保証会社)の同意」が必須である点です。売出価格や配分案に債権者が納得しなければ取引は成立しません。また残債が残る前提で契約を結ぶため、決済日に抵当権抹消と同時に返済計画の和解書を交わす必要があります。
どの時点まで競売を止められる?
原則として開札日前日までに債権者と合意し、裁判所へ任意売却成立の書面を提出すれば競売は取り下げ可能です。ただし差押登記の解除手続きに 1〜2 週間かかるため、配分案は遅くとも開札3週間前 にはまとめる必要があります。なお競売の『申立ての取下げ』は、申立債権者が開札期日の前日までに取下書を提出することで原則可能です(開札後は買受人等の同意が必要)。“任意売却成立書面”自体を要件とするのではなく、取下げ手続が要件です(裁判所BITの手続説明に基づく)。
滞納前でも手続きできる?
可能です。延滞が始まる前に債権者へ相談し「任意売却予告届」を出しておけば、交渉がスムーズに進みやすくなります。市場価格に近い成約額を狙えるため、早期相談は大きなメリットです。
ブラックリストに載る期間は?
信用情報機関CIC・JICCの信用情報に事故情報が登録される期間はおおむね5年間(信用情報の登録期間は手続別・機関別に異なります)。完済後、金融ブラックが消えるまでは新規ローンやクレジットカード発行は難しいと考えてください。
引越し時期は交渉できる?
買主の同意が得られれば最長 1〜2 か月の「猶予期間」を設ける例もあります。ただし原則はあくまでも決済と同時に不動産を引き渡す「同時履行」。買主の同意があればラッキー程度に考えておき、可能な限りすみやかに引っ越しできるよう準備しておきましょう。なお、自分に有利な条件をつけると不動産を売却しにくくなる点も考えておく必要があります。できる限り買主にとってネガティブな条件はつけず、速やかに引き渡しをするべきでしょう。
配分案が通らないケースは?
後順位抵当権者や税金差押えがある場合、配分額ゼロだと拒否されることがあります。その際は「ハンコ代」として数万円〜数十万円を配分案に上乗せすることで合意を得るのが慣例です。先順位の抵当権者(たいていは銀行)もその点は心得ており、交渉がまとまるケースが主流です。
家族や近所に知られるリスクは?
任意売却でも広告や資料に「任意売却物件」と明記するわけではありませんから、近隣に知られる可能性は低いでしょう。価格帯も市場価格に近いため、不自然さが出にくいメリットもあります。
残債が多すぎる場合の対処は?
残債が売却価格を大幅に超えるときは、長期分割や将来の収入増に応じた ステップアップ返済で和解するケースがあります。場合によっては個人再生や自己破産を検討しますが、その場合は不動産会社の守備範囲を超えてしまうため、弁護士に依頼する必要があります。
自己破産とどちらが先?
任意売却→残債確定→自己破産の順が一般的です。売却で残債が減るほど免責後の生活再建が容易になります。一般に、任意売却に強い不動産会社であれば、任意売却と並行して、その後の自己破産をお願いできる弁護士事務所と連携しています。
売却後の税金はどうなる?
任意売却ではマイホームを時価より高く売るケースは少なく、譲渡所得税が課されるケースは少数派。ただし住民税などは滞納中でも課税される点に注意してください。
特例の適用可否を含め、税制面については税理士やファイナンシャルプランナーへご相談ください。
まとめ:競売より有利な任意売却の流れをつかみ実行しましょう

任意売却は競売に比べて最大3割高く売れるといわれています。また、信用情報の回復も早いため、おすすめの選択肢といえます。
競売では、市場価格の6~7割程度での売却を覚悟する必要がありますし、その結果「家を売った後に大きなローン残高が残る」ということになりかねません。
それでは、新しい生活のスタートが切れず、自己破産など考えたくないシナリオに進んでしまう可能性が出てきます。また、税金の滞納がある場合は自己破産でも消えませんから、延々と借金地獄から抜け出せないことに……。
そうならないためにも、任意売却を利用して少しでも有利な条件で自宅を売却してください。
家計再建の第一歩を踏み出すか、競売通知を待つか……決断できるのは今だけです。
今すぐできる次の一手は?
銀行からの督促状が手元にあれば、今すぐ開封して、内容を確認してください。その上で、信頼できる不動産会社に、できるだけ早く相談することをおすすめします。
沖縄県内であれば、トーマ不動産までお問い合わせください。できる限り有利な条件を考え、新生活をスタートするためのサポートを行います。
お問い合わせ|トーマ不動産
県外の方は、任意売却.comという専門サービスを利用してください。
任意売却.com|公式サイト
任意売却専門なので、複雑で危険なポイントが多い任意売却プロセスを、しっかりと進めてもらえます。また「すぐに任意売却の決断ができない」という方は、公式LINEから気軽に問い合わせてみることもできます。


